競争時代だからこそ「競争」と「協業」の共存を【一般社団法人日本医療機器工業会 理事長・松本謙一】

明けましておめでとうございます。
〈明治百五十周年を迎えて〉
今年は明治の元号が続いていれば「百五十年」ゆえ、何かと記念行事も企画されている由。「降る雪や 明治は遠くになりにけり」という句があるが、「明治」は44年5月迄、「大正」は15年1月迄、「昭和」は64年1月迄続いた。
「平成」はメディア等によれば、31年5月に改元と伝えられているがどうなるのであろうか。何れにせよ、世界情勢はこれ迄の北朝鮮を巡る厳しさに加えて、トランプ発言による中東和平まで、きな臭くなってきた。
こうした中で、明治「以前から」はともかく「以後」継続してきた企業は、医療機器業界で何社あるのであろうか。ただでさえ、昨年10月6日の日経紙によれば「大廃業時代」の足音が聞こえてきた。全業種で「中小『後継未定』127万社」という。「血脈」よりは「継続」に力を入れて、何とか「廃業」「転業」は避けて、大切な医療技術を伝承していかねばならない。
〈競争と協業〉
今年は、とりわけ6年に一度の「診療報酬」と「介護報酬」のダブル改訂の年でもある。財政状況と社会保障費とのバランスからみても、厳しい結果が待ち受けているであろう。

そうした中にあって、やたらな「相打ち」となる値引き競争やコンプライアンスに反する様な不正競争に走ることなく、正々堂々と時流に合った企業戦略が不可欠と思われる。
その一例は、製造業における「開発・製造」面での協業でもあり、又、流通業においても「地域包括ケア」という国策のもと、一種の「分業」もあるのではなかろうか。ここにも「IoT」化時代に即した情報技術を、製販共に導入できると信じられる。
〈SUD〉
そうした意味でも又、貴重な医療資源の更なる有効活用、医療費削減という意味合いからも、「R―SUD(単回使用医療機器の再製造)」についての「産・学共同協議会」如きものの検討は早急に行われて然るべきではなかろうか。
〈リベラル・アーツ〉
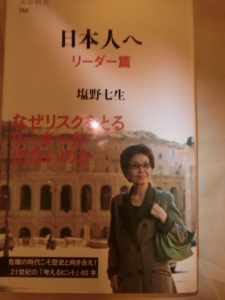
昨年のノーベル文学賞は日系英国人のカズオ・イシグロ氏が受賞した。途端に本屋の店頭には同氏の「日の名残(なご)り」「わたしを離さないで」等、数々の著書が山積みされていた。しかし小生が日曜日に自宅近くの書店で求めたのはそれらではなく、「日本人へ・リーダー編=なぜリスクをとるリーダーが出ないのか(塩野七生)」であった。2時間で読了した。
10月初頭、所用でポーランド・ワルシャワを訪ねた折、週末の一夜はショパン・コンサートでショパ
ンに酔いしれたが、それよりも、通訳を依頼した生粋のポーランド女性・カシャさんの一言。「何故、日本語・日本文化に惚れたのか?」の問いに「芥川龍之介の『河童(かっぱ)・或阿呆の一生』を、最初はポーランド語で読み、後、難関・国立ワルシャワ大学の日本語学科で5年間学んでいる間に、今度はそれを日本語で読破した。」と答えてくれた。
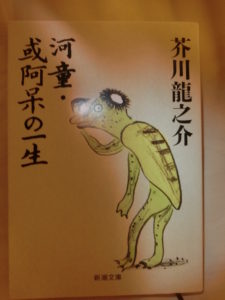
この一言に触発され、あらためて小生も新潮文庫の同書を読んだ。そして想った。これぞ「日本企業の真のグローバル化には、世界との『対話力』を磨くことが不可欠」と。即ち「外国の一流の経営幹部との交流には、自分の本業のみならず、歴史・哲学・文化など、いわゆる『リベラル・アーツ』の話題は欠かせない」と。いかに優秀でも「専門馬鹿」では通用しないということであろうか。
〈イノベーション〉
さりとて昨今は勿論、「IoT・AI・ロボット」等の分野についても素人なりに一生懸命勉強していかないと時流についていけない。
〈結び〉
今年も業界全体が、そして皆にとってハッピーな年であることを祈念して筆を置きます。
―以上―