未来を想像し、創造するには ~ 本を読め、人に会え、考えよ、そして行動を起せ ~【一般社団法人 日本医療機器産業連合会 会長/一般社団法人 日本医療機器工業会 理事長・松本謙一】
明けましておめでとうございます。
〈今年はどんな年〉

昨年は、年号も「平成」から「令和」に変わり、新天皇も「即位礼正殿の儀」で「国民の幸せと世界の平和を願い」と述べられ、国民の共感をよびました。また、10月には吉野彰先生がノーベル化学賞を受賞されるなど、おめでたい事もあった反面、忘れられない台風被害など、世界的にも政治・経済あらゆる面で激動の一年でした。
年が変わって今年は「子年」(ねどし)です。子年は十二支の一番はじめ、干支頭ともいわれ大変縁起の良い年とされています。
ねずみは五穀豊穣(ごこくほうじょう)と商売繁盛の神「大黒天」の使者であり、その名は「寝ず身」にも通じ、よく働くことで財を成し、招福・蓄財のお守りにもなるともいわれます。
この子年が、来る十二年間の多幸の「はじまりの年」となるよう願いをこめて、この拙文を書いておりますが、ちなみに、私事にわたり恐縮ですが、小生は子年であり、「年男」です。神仏の教えのとおり「世の為、人の為」に努力する所存です。
〈未来を想像し創造する〉
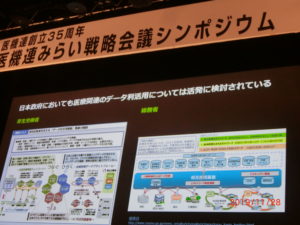
その昔、「文藝春秋」誌の名編集長といわれた池島信平氏が「本を読め、人に会え、そして旅に出ろ」との名言をはかれた由。けだし至言と思います。医療・介護の「未来を想像し創造する」為には、徒らに唯「AI・IoT・ロボット」等のキーワードにおどらされているのみではなく、「本を読み、人に会い、旅に出て感性豊かに行動を起す」ことに尽きるのではないでしょうか。
〈厳しい現実への対応〉
未来を考える前に、勿論、厳しい「現実」が立ちはだかっています。昨年、10月初め厚生労働省は診療実績の乏しい全国424の公立・公的病院を実名で公表し、再編や縮小を促しました。これには様々な立場から種々のコメントが出されてはいますが、一方で政府は病気が発症した直後の「急性期」の患者向けの病院ベッドを2025年迄に減らす「地域医療構想」を進めています。
これらに対応して業界側も徒らに手をこまねいている訳にはいきません。医薬品業界でも、改正薬機法の成立を機に「オンラインでの服薬指導」や、ジェネリックの8割以上の普及などの他にも、医療費削減に対応出来るよう施策を考えています。医療機器業界でも種々の方策を考えていかなければなりません。
〈R‐SUDの推進〉
「単回使用医療機器(SUD)再製造推進協議会(JRSA)」が活動を開始して2年余。その活動が実って、昨年8月30日、日本S社の製品が第一号として承認されました。今後とも、夫々のガイドライン等の検討も含め、課題は色々あるでしょうが、一社完結型よりも数社協業型方式に則し、病院会など使用者側団体や行政との協調を旨として推進していけば、欧米と同様、日本でも環境対応・コスト削減効果などから、更なる一歩を踏み出せることでしょう。中医協にも提言されていることですし、今年に期待をかけましょう。
〈今年のキーワード〉
日本の医療機器産業のキーワードとしては、「イノベーションと海外展開」だと思います。但し、「イノベーティブなハード・ソフトの開発」にはあえて「競業」も辞さずという心意気が必要でしょうし、「海外展開」にしても、余程、当該国の「ニーズ・シーズ」を捉えなくては、徒らに見当外れの「製品・市場」開発になるでしょう。
〈コンプライアンス〉
昨今、「医薬品卸」の談合事件がメディアに大きく報じられましたが、医療機器の公正競争規約からは「長期貸出し・違法立ち合い」なども当然、心しなければならないし、「不具合報告」の面からは、当然、市販前後の「質」の担保も厳に心すべきことでしょう。
〈むすびに〉
以上、本年も厳しいことに変わりはないでしょうが、今年は「子年」のことでもあり、業界の皆様におかれましても、良き一年でありますよう、心から祈念して筆を置きます。
―以上―