データ利活用の方向性探る【医機連】
「みらい戦略会議シンポ」開催
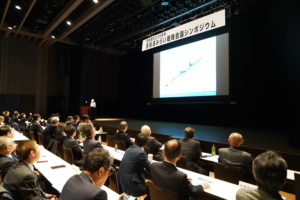
日本医療機器産業連合会(会長=松本謙一氏、医機連)は、今年が創立35周年の節目にあたることから、医療機器産業界のさらなる発展をめざして、11月28日㈭午後2時から、東京・中央区の日本橋三井ホールで「医機連みらい戦略会議シンポジウム」(テーマ=ソサエティ5・0を支える医療機器産業をめざして-データ利活用について考える-)を開催した。
ソサエティ5・0を支える産業めざす
医機連は2018年10月に医機連産業ビジョン『ソサエティ5・0を支える医療機器産業をめざして』を制定し、19年4月に『医機連みらい戦略会議』を発足させた。
シンポジウムでは医機連産業ビジョンで掲げたテーマを踏まえ、データ利活用やサイバーセキュリティをテーマに、それらの課題や方向性について、講演やパネルディスカッションを繰り広げた。開会にあたり、医機連副会長で医機連みらい戦略会議の渡部眞也議長が登壇。『医機連みらい戦略会議のめざすもの』をテーマに講演した。

渡部議長は「ソサエティ5・0はIoT(モノのインターネット)やロボット、AI(人工知能)などの先端技術を活用して、人が生き生きと快適に暮らせる社会。医療機器がその新しい社会の期待にどう応えて行くかが大きなテーマになっている」と前置き、ソサエティ5・0をめざし医療の世界で起きている変化を含め、医機連みらい戦略会議を発足させた背景を説明した。
パーソナルへルスレコードを活用へ
医療の世界の中で情報化がもたらす変化としては「パーソナルへルスレコード(個人健康情報管理)は今後、さまざまなデータがつながっていくことで、色んな変化をもたらす。例えば日ごろの活動やバイタル、ライフログが医療現場の臨床に使われるようになる。患者のケアは病院だけでなく、在宅を含めてできるようになる。それを支えるIoTデバイスもさらなる進化が求められる」と健康・医療・在宅のすべての領域でのデータ利活用の推進を促した。
医療で活用されているAIについては「医療の中でAIは画像診断領域が一番進んでいる。そのほか、ゲノムや治療、医薬品開発、オペなどの領域で活用され、推定で1兆5000億円ほどの市場規模になる。日本ではAIホスピタルプロジェクトが昨年から始まっている。AIを使って精神的な患者中心の医療の実現をめざしており、多くの関心を集めている」と説明した。
医療データベースの構築にふれては「これまでに色んなデータの共有が進められてきたが、さまざまな課題に突き当っている。ポータビリティであったり、データを出す側のメンタリティであったり、スムーズにデータベースの構築が進まない過去がある。これは乗り越えないといけないテーマでもある。医療データの活用は臨床だけでなく、患者へのインフォームドコンセントや、医療スタッフ間のコミュニケーション改善にもなり、働き方改革にもつながる」とした。
手術領域でのイノベーションに言及しては「90年代に内視鏡手術が広まった。99年にダビンチ(手術支援ロボット)が世界で初めて導入され現在、日本でも300台が稼働している。低侵襲のメリットが進んできたが、次のイノベーションが何かというと、データの利活用だと思われる。術者とテクノロジーとインフォメーションがつながり、新しい価値を生み出すだろう。また、SCOT(スマート治療室)プロジェクトは日本の医工連携の成功例だと思う。医療機器関連企業20社以上と医療機関が連携し、各種医療機器・設備を接続し、データを活用しながら開発に取り組んでいる」と紹介した。
医療の中にデジタルへルスという分野が誕生していることに関しては「デジタルへルスは予防や健康に関わる分野で、コ・メディカル向けであったり、生活者向けであったり、数多くのデバイスやソフトウェアが出てきている。非常に多くの企業が参入してきている。間違いなくイノベーションを起こす分野だと考え、産業界としても後押ししていきたい」とした。
医工連携から医工共創へ
政策提言や官民連携支援を推進
医療の世界で起きている変化を踏まえ「医療機器産業のテーマは医療の高度化、早期診断、医工連携、データイノベーション、デジタルへルス--など、健康・医療・在宅のすべての領域に広がり、医療機器への期待は増している。その一方でグローバル展開や安全、サプライチェーン、人材--なども非常に大事なテーマとなる。このようなことが背景となり、医機連みらい戦略会議を発足させた」と医機連みらい戦略会議発足の経緯を説明した。
医機連みらい戦略会議については「みらい戦略会議は産業政策やデータ利活用、サイバーセキュリティを医機連の知恵を結集し、外部組織との積極的なコラボレーションを図りながら、政策提言や官民連携支援などに取り組んでいく。また、中国で設立された医療機器団体との連携も視野に入れている」と活動内容を挙げた。
データに基づく健康・医療の活性化に向けた課題のふれては「ナショナルプラットフォームの整備として、国民にとって自分の健康・医療情報が社会の役に立つよう、積極的にデータが提供される環境作りのほか、データの紐付け(医療ID導入等)や高品質データ(AIの教師付きデータ等)など利活用できる価値の高い医療データの整備が課題となる。あるいは医療機器産業界として協創領域を考え、事業の経済性の確保に向けた活動内容などについて議論していきたい」との方針を示した。
最後に「医機連みらい戦略会議が医療機器の未来を創っていく、ひとつのドライビングコースになればと思っている。社会的にも経済的にもインパクトの大きいグローバルな事業を創出していきたい。また、イノベーションは現場から生まれるのは間違いない。複数の研究機関、医療機関、企業の連携による『医工共創』により、プラットフォーム(特にデータ)をベースにしたイノベーションを創出していきたい」との思いを表明した。
このあと、シンポジウムでは日本医療研究開発機構産学連携部の竹上嗣郎部長や国立精神・神経医療研究センター臨床研究支援部の中村治雅部長、徳州会インフォメーションシステムの尾﨑勝彦社長、デロイトトーマツサイバーの丸山満彦執行役員--の4氏が、それぞれの立場で、医療データ利活用やサイバーセキュリティに関する最新情報をテーマに講演を行った。引き続き、パネルディスカッションではデータ利活用の課題や方向性について議論を展開した。